
人生100年時代、老後資金はどうする?50 代 のうちに備えておくべきこと
UPDATE
8分

CONTENTS
老後資金はどのくらい必要?

人生100年時代、「長生きできるのはうれしいけれど、老後資金が足りるかどうか心配」という方も多いのではないでしょうか。数年前には、「老後2,000万円問題」が大きな話題となり、老後の生活への不安が関心を集めました。
この「2,000万円」という金額は、2019年に金融庁が発表した報告書に由来しています。報告書によると、夫婦の老後に必要な生活費は年金だけではカバーできず、2,000万円程度の資産を自分で準備しておく必要があるとされています。もちろん、「2,000万円」という金額はあくまでも1つの試算に過ぎず、全員が老後に年金+2,000万円が必要なわけではありません。人によって理想の老後は異なり、老後に必要な資金も異なるので、2,000万円という金額に惑わされず、楽しく充実した老後を過ごすために必要な資金を見極めて老後に備えることが大切です。
では、どうすれば自分に必要な老後資金の目安を知ることができるのでしょうか?
総務省の家計調査によると、2023年度、65歳以上世帯の平均支出は以下の通りでした。
単身世帯:14万9,033円
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040193373
2人世帯:29万4,116円
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000000330002&cycle=8&year=20231
つまり、単身世帯の場合は1か月で平均約15万円、1年間で約180万円が、2人世帯では、1か月で約30万円、1年間で約360万円が平均的な生活費ということになります。
一方、日本の国民年金の満額(2024年4月時点)は1人当たり月額 65,141円 、厚生年金の場合は標準的な夫婦2人への支給額は月23万483円(2024年度)で、いずれも平均支出を下回っています。年金だけでは生活が賄えないとなると、やはり、自分で老後資金を準備しておくのが賢明です。
老後資金を増やすには、どうすればいい?

では、年金+αの老後資金を準備するには、どうすればよいのでしょうか。
実は、この問いに関する答えは実にシンプルです。
まず、働いて収入を増やし、支出を抑えて貯蓄すること。そして、貯蓄の一部を投資に回して増やすことです。
50代はまだまだ働き盛り!できるだけ長く働こう
かつての日本では、60歳で定年退職して老後生活に入るライフスタイルが主流でした。しかし、今は働き方もライフスタイルも多様化の時代。何歳まで働き続けるかは本人次第ですし、その気になれば年齢に関係なく働くことが可能です。特に昨今は幅広い業界で労働力不足が深刻化しており、30代、40代はもちろん50代以上の人材にも活躍のチャンスはたくさんあります。中でも特定の分野で豊富な経験がある人、専門的な知識やスキルがある人は即戦力として、幅広い業界で歓迎されています。「もう50代だから」などとあきらめずに、ぜひ自分の経験を生かして、できるだけ長く働き続け、老後資金をためましょう。また、働き続けることで、さらに経験やスキルを磨けば、一般的に「老後」と言われる年齢になっても働き続けられる可能性が高くなり、その分、経済的に余裕のある老後を過ごせる可能性も高くなります。
働き続けることのメリットは、収入だけではありません。定年後に何もしないで家にいると社会との接点が弱くなってしまいがちですが、働き続けると、仕事を通じて他者と関わり、社会とつながりを持ち続けることができます。それが心身の若々しさにつながり、よりアクティブに老後の生活を過ごせるようになります。会社員だった方もフリーランスや個人事業主、アルバイトやパートなど、その気になればいろいろなスタイルで働くことが可能です。定年前の50代のうちから、老後の働き方について自分なりに方針を決め、リサーチしておくことをおすすめします。
無駄な支出を控えよう
収入を増やすと同時に無駄な支出を減らすことで、より効率的に老後資金をためることができます。「無駄遣いなんてしていない」と思っている方も、実際に使った金額を書き出してみると、意外と無駄がみつかるもの。最近は簡単に家計を記録・分析できるスマホアプリも多数登場しています。まずは1か月、家計簿をつけて支出を可視化してみましょう。家計を見直す際のポイントは以下の通りです。
固定費の見直し
固定費は毎月必ず支出が発生するため、ここを削減できると大きな効果が得られます。
・ 住宅費(家賃やローン返済)
家賃や住宅ローンの金額が高すぎる場合、引っ越しを検討する、またはローンの借り換えを検討してみましょう。
・ 保険料
不要な保険や過剰な補償内容がないかを見直して、必要な補償内容だけに絞りましょう。
・ 通信費(携帯電話・インターネット)
契約内容を見直したり、格安SIMを利用することで通信費を削減できます。
・ サブスクリプション
動画や音楽の配信アプリ、新聞・雑誌の購読など、使っていないサービスは解約しましょう。
・ 各種会費
ジムの会費やクレジットカードの会費など、自動引き落としなどで無意識に支払っている会費を見直し、本当に必要なもの以外は解約しましょう。
変動費の見直し
変動費は月ごとに変動する支出ですが、節約しやすい部分でもあります。
・ 食費
外食やコンビニでの買い物を減らし、自炊を心がける。まとめて作り置きや冷凍保存で食材を無駄にせず、買い物は計画的に。
・ 交際費
無駄な飲み会や娯楽への支出を見直し、あらかじめ設定した予算内で楽しむようにしましょう。
・ 衣類・雑貨・化粧品など
セールや割引を活用し、必要なものだけ購入する。衝動買いを減らすために、買う前に1日置いて冷静に判断しましょう。
日常的な支出の見直し
日常的な支出を見直すことも、長期的に見れば大きな貯蓄につながります。
・ 光熱費
節水や節電を意識する。例えば、エアコンの温度設定を見直す、使わない部屋の電気を消すなど。
・ 交通費
なるべく公共交通機関や自転車、徒歩で移動しましょう。運動不足も解消できて一石二鳥です。
支払い方法の見直し
支払い方法を見直すことで、支出を効率よく管理できます。
・ ポイント還元
クレジットカードやデビットカードを利用してポイントをためましょう。ただし、クレジットカードの使い過ぎには要注意。月々の支払い金額を把握して、予算内に収めることが重要です。
・ リボ払いや分割払いを避ける
分割払いやリボ払いに頼らず、なるべく一括で支払うことで利息の支払いを減らしましょう。
生活の質と支出のバランスを大切に
節約しすぎて生活が窮屈になると、精神的にも疲れてしまいます。生活の質を保ちながら支出を見直すために、以下のような工夫をしてみましょう。
・ 予算を決める
節約のために趣味や娯楽費を完全にゼロにしてしまうと、長続きしません。月ごとに予算を決めて、その範囲内で楽しみながら貯蓄をしましょう。
・ まとめ買いやセールの活用
必要なものをセール時にまとめて購入したり、割引クーポンを活用したりして賢くショッピングを楽しみましょう。
予算管理の習慣化
支出を意識的にコントロールするためには、「予算管理」を習慣化することが大切。毎月の支出をカテゴリーごとに予算化し、その範囲内に支出を収めることで、無駄な支出を防ぐことができます。
見直すポイントがわからないという方は、ファイナンシャルプランナーなど専門家の家計診断を受けてみるのも一案です。
意外と簡単!資産形成に取り組もう
支出を見直して貯蓄が増えたら、その一部で資産形成に挑戦しましょう。ハイリスク・ハイリターンの商品を避けて投資すれば、安全に老後資金を増やすことも可能です。老後への備えによく活用されている投資商品は、比較的低いリスクで始められ、税制優遇も受けられるNISAとiDeCoです。
NISA(少額投資非課税制度)
NISAは、投資で得た利益が非課税になる制度です。通常、株式や投資信託などから得た配当や分配金、売却時の譲渡益は、原則として所得税や住民税の課税対象です。しかし、NISA口座で投資した一定の購入分については、その配当や分配金、譲渡益が非課税になります。NISAを利用するためには、金融機関(証券会社や銀行、郵便局など)でNISA専用口座を開設する必要があります。NISA口座は、日本国内に住む18歳以上の方なら誰でも、口座を開設することができます(1人につき1口座)。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、税制優遇を受けながら自分で老後資金を積み立てることができる制度です。拠出金(掛け金)は全額所得控除対象で、運用益は非課税。積み立てた資金は、60歳以降に一時金または年金形式で受け取ることができ、受け取る際にも税制上の優遇があります。対象者は20歳以上60歳未満で、職業によって拠出限度額が異なります。運用商品は投資信託や定期預金などから自分で選ぶことができますが、60歳まで引き出せないため、長期的な資産形成を目的に利用することが大切です。
NISAもiDeCoも、資産形成をサポートしてくれる制度ですが、リスクは決してゼロではありません。万が一損失が出た場合も、原則として自己責任です。利用する際は余裕資金の一部を充てるだけにとどめ、老後資金を全額失ってしまうような事態に陥らないようにしましょう。
健康習慣を身に着け、スキルアップして働き方の選択肢を増やそう!

ここまで老後への備えとして「収入を増やす」、「貯蓄を増やす」、「投資をする」の3つをご紹介してきました。これら3つを実践するのに欠かせないのが、健康です。年齢を重ねることで心身の不調や体力の衰えなどはある程度仕方のないことですが、50代はもちろん60代、70代になっても安心して働くためには、心身の健康が欠かせません。1日も早く、健康管理に積極的に取り組み、特に重篤な病気の原因になる生活習慣病の予防を心掛けましょう。健康習慣を身に着け心身が健康な状態で老後を迎えられれば、健康寿命も長くなり、より積極的に仕事や趣味に向き合うことができます。
健康習慣とともに身に着けておきたいのが、スキルアップを図ることです。現役時代から仕事と並行して資格を取得する、英語をブラッシュアップするなどのほかに、PCスキルを磨くことも有効です。例えばエクセルで複雑な数式なしにデータの整理や分析ができるピボットテーブルや、膨大なデータから必要な情報を見つけられるVLOOKUP関数をマスターすることで、定年退職後の再就職やフリーランスとしての独立の際に、仕事を得る上での大きな武器となるでしょう。ある程度の年齢になると、誰でもだんだんと無理がきかなくなりますが、通勤時間や休日の自由時間などを活用して、健康に留意しながらスキルアップを図り、仕事の選択肢を広げていきましょう。
また、会社員として働いている人は会社の福利厚生制度で資格試験の費用などに補助が得られる場合があります。利用できる制度がないか、今一度確認してみるとよいでしょう。そして、老後に独立を考えている人は勤務先で禁止されていない場合は、副業にチャレンジしてみるのもおすすめです。老後にやりたいと思っている仕事をやってみることで、本当に自分に向いているのか、需要があるのかなどを、実体験として確認することができます。
老後を楽しくするのは、自分次第!
ここまで見てきたとおり、経済的に余裕をもって安心して老後を過ごすためには、「収入を増やす」、「節約する」、「投資する」、「スキルアップする」などのアクションが欠かせません。言うまでもなく、そのアクションの主人公はほかの誰でもなく、皆さん自身です。つまり、どんな老後を過ごすのかを決めるのは、皆さん自身だということ。「老後なんて、つまらない」と思って何もしないと、本当につまらない老後になってしまうおそれがあります。でも、人生100年時代の長い老後をずっと後ろ向きな気持ちで過ごすのは、本当にもったいないことですよね。加齢による心身の変化は柔軟に受け止めつつも、「できるだけ長く働き続ける」、「趣味と老後を両立させる」など自分なりの目標を立てて、前向きに老後と向き合いたいものです。老後は長い間、勉強や仕事、子育てなどに頑張ってきた自分へのご褒美のような大切な時間。わくわくと楽しみながら過ごせるように、若いうちから準備を始めましょう。
まとめ
老後に必要な資金は人によって異なる。楽しく充実した老後を過ごすために必要な資金を見極め老後に備えよう。年金だけでは生活が賄えないのなら、自分で老後資金を準備しておくのが賢明。
老後資金を増やすには、働いて収入を増やし、支出を抑えて貯蓄すること。そして、貯蓄の一部を投資に回して資産形成に取り組もう。
現役で働いているときから健康習慣を身に着け、スキルアップを図ろう。スキルを研くことは、定年退職後に働く際にも大きな武器となる。
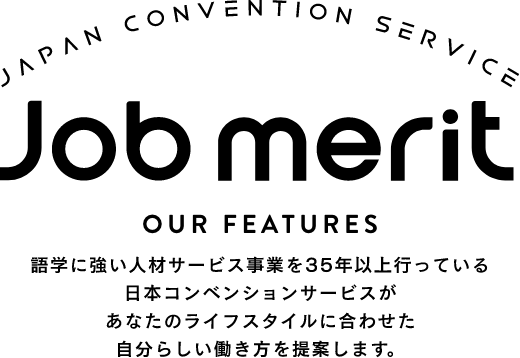
ジョブメリでお仕事を探そう
語学・イベント案件に強い!
正社員・派遣社員からアルバイトまで働き方いろいろ!
あなたのキャリアプラン・ライフスタイルにあったおしごとをジョブメリで探そう
このカテゴリーのおすすめ記事





