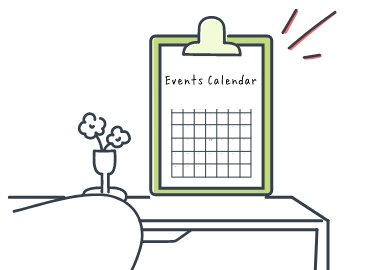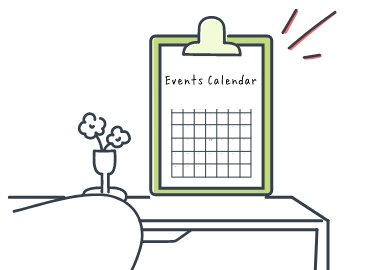
SDGsに関わる仕事とは?変化するMICE事業とSDGsの関係
UPDATE
5分

CONTENTS
もはやSDGsは当たり前!MICEはどう変わった?
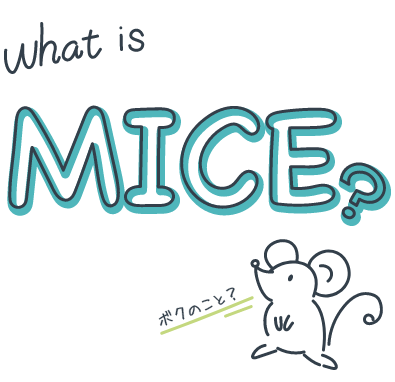
MICEとは
MICE(マイス)とは、企業等の会議(Meeting)、企業等の行う報奨・研修旅行(インセンティブ旅行)(Incentive Travel)、国際機関・団体、学会等が行う国際会議 (Convention)、展示会・見本市、イベント(Exhibition/Event)の頭文字を取って作られた造語で、これらのビジネスイベントを指す総称です。世界中から参加者が集まるMICEは開催地域への経済効果が大きいことから、日本でも国や各地方自治体がMICE誘致に力を入れています。UIA(国際団体連合)によると、2019年の世界全体における国際会議開催件数は1万3,144件(前年比プラス2,109件)。同年の日本における国際会議開催件数は、719件で世界5位でした。
*出典:日本政府観光局(JNTO)2019年国際会議統計「世界規模で見る国際会議の動向」
コロナ禍から順調に回復
2020年以降は新型コロナウイルスの影響で世界的にMICEの開催件数が激減しましたが、コロナ禍が収束傾向に転じた2022年以降は世界的にMICEの開催が再開されました。日本政府観光局(JNTO)が発表した「2022年国際会議統計」によると、2022年に日本で開催された国際会議は、前年比19.1倍の553件に。参加者総数は、前年比5.9倍の32万5,752人(うち外国人参加者数3万3,787人)で、コロナ禍からの着実な回復が見られました。
*出典:日本政府観光局(JNTO)2022年国際会議統計「日本で開催された国際会議の動向」
MICEは、開催地域を中心に大きな経済波及効果を生み、各都市のブランド力や競争力を向上させるだけでなく、開催そのものが、社会課題の解決の場となり、イノベーションを生み出す機会を提供する場となります。そのため、MICEは今後もさらに重要性を増すものと見られています。
SDGsへの配慮が重視されるようになった理由は?
コロナ禍が一段落したことで、再び世界各地でMICEが盛んに開催されるようになる中、その開催地の誘致競争も過熱しています。
これまで、MICE誘致に力を入れている各国や自治体では、立地や治安の良さ、歴史や文化、自然環境の豊かさなどをアピールして誘致合戦を繰り広げていましたが、近年はこれらに加えてSDGsへの配慮をアピールポイントとする例が増えています。
というのも、MICEの開催はたくさんの人や物の移動を促し、経済的・社会的に大きな効果を生み出す一方で環境負荷の高いことが課題となっているからです。近年では、MICEの開催地を決めるにあたって、対象となる国や地域がサステナビリティに配慮した取り組みをしているかどうかが、より重視される傾向にあります。
国連は2015年の「持続可能な開発サミット」で、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標としてSDGs(Sustainable Development Goals)を採択しました。それ以降、SDGsを達成するためのアクションを起こす企業や自治体が増える中、それらの事業活動の一環として行われるMICEにもSDGsへの配慮が求められるようになったのは、当然の流れと言えるでしょう。
さらにコロナ禍の間には、感染拡大予防のため、多くのMICEがオンラインまたはオンラインとオフラインを併用する形で開催されました。今ではすっかり定着した感もあるオンライン開催ですが、時間や移動のコストがかからないというメリットがある反面、「お互いの表情や雰囲気をつかみづらい」、「通信状況や機器の調子などの影響を受けやすい」などのデメリットが指摘されることもありました。一方で、SDGsの観点から「航空機での移動を伴わないので二酸化炭素の排出量を抑えられる」、「会場から出るごみの量を減らせる」といった特長が紹介されるようになりました。コロナ禍を契機としたオンラインに対する意識の変化も、SDGsに配慮した環境に優しいMICEを開催するという流れにつながっているのかもしれません。
日本の強みは?
こうした背景から、日本でも国を挙げてSDGsを意識したMICEの誘致に乗り出しています。SDGsの観点から日本が世界に打ち出している強みには、主に以下のような点があります。
環境負荷が低く効率的な鉄道交通網
迅速、安全かつ時間に正確な日本の鉄道は、日本全国をほぼもれなく網羅しており、新幹線がMICEの開催地となる主要都市間をつないでいます。また、国内の各都市では、環境負荷の少ない水素バスや次世代型路面電車システムであるLRTが導入されるなど、クリーンな公共交通機関の利用が促進されています。
代替エネルギーの促進
日本では多くの企業や自治体が2050年のカーボンニュートラル達成に向けて太陽光や風力、水力や水素といった再生可能エネルギーの導入を進めています。中でも太陽光発電の発電量は世界第3位(2021年・IEAのデータより)となっています。MICE会場にも、例えば、利用する電力の100%に再生可能エネルギーを利用するグリーン電力化を実現している愛知県国際展示場や、廃棄物のリサイクル率90%を達成したパシフィコ横浜など省エネや代替エネルギーの利用を進める会場が増えています。
歴史や文化の伝承
利便性の高い大都市だけでなく、日本には、神社やご神木を囲む鎮守の森が各地にあり、生態系の保全や生物多様性の面から高い評価をされるようになっています。その周辺には、循環型の社会を実現してきた伝統工芸を体感できる施設も多く、伝統的な保存食など、海外に向けて発信できるものが多数あります。地域ごとに伝承されている、独自の歴史や多様な文化は海外の方にとっても魅力的なソフトとなっています。
事例紹介:
JCSイベントでの
SDGsの取り組みとは?

では、日本におけるMICE施設の設営ではSDGsについて具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか。具体例として、1967年に日本で最初のコンベンション運営企業として創業した日本コンベンションサービス株式会社(JCS)の事例を見てみましょう。
JCSは2012年に、持続可能性に配慮したイベントを運営する組織の仕組みを定めた国際基準である「ISO 20121」を日本で初めて取得し、それ以来「ISO 20121」を運用したコンベンションの実績を重ね、その件数は2024年3月現在で227件に上ります。
「ISO 20121」は2012年のロンドン五輪、パラリンピックで採用され、史上もっとも環境に優しい大会として高い評価を得て、東京五輪、パラリンピックでも採用されるなど、ますます関心が高まっている国際認証です。
さらに2023年には、「ISO 20121」を含むマネジメントシステムの審査機関であるBSIグループジャパン株式会社が、イベントサステナビリティの豊富な運用経験と知見をもつ同社を、「アソシエイト・コンサルタント・プログラム」のメンバーとして選定し、現在17名のコンサルタントが在籍しています。
JCSによるハード面での取り組み
JCSでは、これまでの、さまざまなコンベンションにおける豊富な経験や実績を生かし、MICE施設の開発・企画・運営を手がけています。選ばれる会場になるためには、建物自体の省エネやバリアフリー、ダイバーシティに対応したアクセシビリティが大切で、建物内のスロープや多目的トイレの設置、点字での表示や授乳室の用意などに取り組んでいます。
JCSによる会場での取り組みの事例
コンベンション会場で同社が取り組んでいる事例を紹介します。
えがおのはしプロジェクト(紀尾井カンファレンス)
イベントで余った未開封のお弁当を、その日のうちに子ども食堂に届ける。必要とする人に食べてもらうことで、フードロス削減に貢献しています。
https://www.convention.co.jp/activities/foodwastereduction/
オリジナルデザインのパウチ水の提供(JCSがグッズとして制作)
会場で提供する飲料水をペットボトルからオリジナルデザインのパウチに変更。パウチに変更することでプラスチックごみを約70%削減することができます。パウチには同社の社員の行動理念(Unite、Change 、Professionality、Love、Sincerity)を印刷して、参加者に周知を図りました。
看板の再利用
企業イベントは1年のうちに同様のイベントを開催することがあります。イベント会場では、会場などのステージで使用するメインのパネルや場内案内のためのサイン看板など、さまざまな種類の看板が使用され、大規模なイベントではその数が50枚を超えることもあります。そのため同社が運営するイベントでは、サイズ、規格などの条件が整えば、看板や備品の再利用や、クライアント企業にて再利用可能なデザインの提案を行なうなどの取り組みを行っています。再利用することで、サステナブルなイベントが運営できるだけでなく、看板の制作・廃棄費用も削減できます。
フードロス対策への取り組み
国際会議では参加者のために食事の手配が必要となりますし、食の多様性に配慮することも重要です。ベジタリアン食やヴィーガン食、ハラル食などを選択する参加者を事前に把握する必要がありますし、当日のキャンセルなどへの備えも必要です。同社では、参加登録時に現地参加かオンライン参加かを把握することで、過剰発注を防ぐ取り組みを行うほか、弁当不足に備えるためにキッチンカーを手配するなどの工夫も行ってきました。また、弁当やビュッフェの準備ではなく、会場周辺で利用できるランチチケットの配布をすることで、参加者に会場周辺を散策する機会を提供すると同時にフードロスにつなげることができました。
こうした取り組みにより、一定の成果を出すことが施設や主催企業にとって非常に大きなメリットになるため、同社ではお客さまに求められるサービスを提供するのはもちろん、SDGsに配慮した新たな施策を実行するために、国内外の情報収集に努めて優れた事例を参考にするなどの努力を続けています。
見方を変えると、施設運営の仕事が、社会貢献やボランティア活動などに関心があり、SDGsに関わる仕事がしたい人にとっても、最適な活躍の場となるかもしれません。
Z世代の若者が取組む
啓発事業とは?
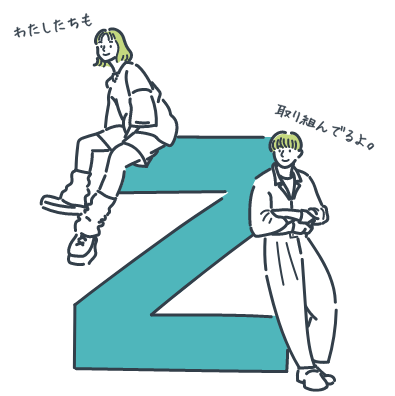
SDGsを意識したMICE運営は、運営に関わる全てのスタッフがSDGsを正しく理解し、目標を共有して取り組むことが欠かせません。そのためには、コンベンションやイベント期間中もしくはコンベンション会場内だけでなく、日常の業務でもSDGsへの意識を社員が共有しておく必要があります。
各社では下記のような取り組みが始まっています。
再生可能エネルギーを利用し、イベントのCO2 排出量をゼロにすることを目指す
ごみの分別に取り組みリサイクルを徹底する
オンラインでの受付を導入し、ペーパーレスを実現する
提供する飲食のメニューを、フェアトレードによるもの、あるいは地元食材を利用したものにする
こうした対応の広がりが、今後のSDGs を意識したMICEの運営の定着や進化につながることが期待されています。新卒社員や若手社員といったZ世代の若者が中心となってSDGsを意識したMICE運営に取り組んでいる会社もあります。SDGsに関わる仕事に関心のある方にとっても、ご紹介したMICE事業は大きな可能性を感じるものではないでしょうか。
まとめ
世界中から参加者が集まるMICEは、日本でも国や各地方自治体が誘致に力を入れている。近年SDGsへの配慮をアピールポイントとする例が増えている。
日本コンベンションサービス株式会社(JCS)では、コンベンションのハード面や、会場内での取り組みを通じてSDGsを達成するための取り組みを行っている。
SDGsを意識したMICE運営には、関わる全てのスタッフがSDGsを正しく理解し、目標を共有して取り組むことが欠かせない。こうした対応の広がりが、SDGs を意識したMICEの運営の定着や進化につながることが期待される。SDGsに関わる仕事に関心のある方にとっても可能性のある仕事だといえる。
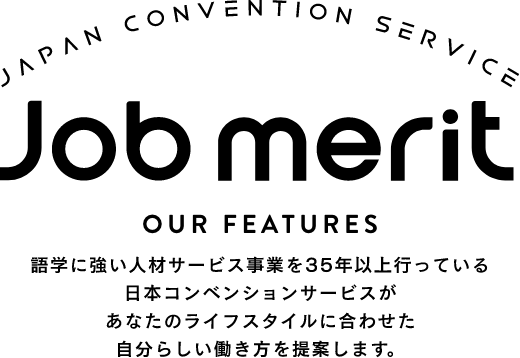
ジョブメリでお仕事を探そう
語学・イベント案件に強い!
正社員・派遣社員からアルバイトまで働き方いろいろ!
あなたのキャリアプラン・ライフスタイルにあったおしごとをジョブメリで探そう
このカテゴリーのおすすめ記事