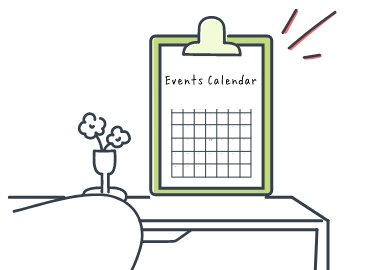ベテラン通訳者直伝!リスニング力UPにおすすめのトレーニング法とは?
UPDATE
10分

CONTENTS
通訳になったきっかけは?

現役で大活躍中のベテラン通訳者さんお二人にお話を聞きました!
―ベテラン通訳として引っ張りだこのお二人ですが、これまでのキャリアや通訳になった経緯を教えていただけますか?
Tさん:私はアメリカで生まれ育ち、アメリカの大学を卒業後にアメリカや日本の企業で働いたあと、独立してフリーランスの通訳になりました。日本での経歴は英語を使った事務職からスタートし、日本の大学でアカデミック・ライティングを教えたり、企業での英語講師を務めた時期もあります。徐々に通訳業務の割合が高い企業でのお仕事につくようになり、インハウス通訳者を経て、6年前に完全にフリーランス通訳者として独立しました。と言っても、計画的に大学で教えようとか通訳になろうとか考えて意図的に動いたわけではなく、周囲の方々から「これ、やってみない?」、「手伝ってほしい」と言われたことを一生懸命取り組んできた結果、通訳になった、という感じですね。
Nさん:そういう方が多いですよね。実は私も大学卒業後しばらくの間は商社で働いていて、英語とはあまり縁のない仕事をしていました。でも、当時付き合っていた人と別れたのを機に心機一転を図るべく、仕事を辞めてアメリカの大学院に進学しました。最初は全然英語がわからなくて、すごく苦労しました。それでも何とか博士号まで取得して、さあ、どうしようというときに、翻訳家として活動していた今の夫に出会い、彼に「やってみたら?」と誘われて、1996年にフリーランスの翻訳・通訳として仕事を始めました。もう、30年も前のことですね。最初の20年はアメリカで働いていたのですが、2012年に日本に帰国して通訳に専念することに。また、5年前にやはり知人からお声がけいただいて都内の女子大で英語を教えています。最初は非常勤講師として教えはじめ、今は特任准教授に。教えることによる学びも大きいので、通訳と准教授の両立ができるようになって本当に良かったなと思っています。
―今日は特にリスニング力をメインテーマにお話を伺いたいのですが、普段、通訳のお仕事をする中でリスニング力の大切さを実感する場面はありますか?
Tさん:リスニングは通訳の基本というか、リスニングができないと通訳はできないので、常に重要さは実感しています。
Nさん:ダニエル・ジルの「努力モデル」理論でも通訳に求められる4つの努力の1番目にリスニングが挙げられています。
<参考>努力モデル
「リスニングと分析(Listening and Analysis=L)」
「発話産出(Production=P)」
「短期記憶(Memory=M)」
「調整(Coordination=C)」
プロになってもリスニングのトレーニングが必要な理由は?

―リスニングで苦労された経験はありますか?
Tさん:もちろん、あります。特に最近は英語が母国語ではない国の人たち(インドやシンガポールの方)の英語を訳す場面が増えていて、いわゆる正統派ではない、訛りや癖のある英語の聞き取りに苦労することも多いですね。
Nさん:確かにひと昔前に比べると、非ネイティブの方の通訳をすることがぐっと増えましたね。世界的に見ても英語を話す非ネイティブの方は増え続けていて、最近では「World Englishes」といって、非スタンダードな英語を研究対象にした学問も登場しているほどです。非スタンダードな英語が各地で独自の変化を遂げていて、同じ英単語でも本来とは違う発音、違う意味で使われているケースも珍しくありません。例えば先日はフランス人の方が「brochure」という単語を使ったんです。これは通常、「会社案内」という意味で使われることが多い単語ですが、どうにも意味が通じないので、確認してみると、そのフランス人はこれを「プレゼン資料」という意味で使っていたんですよね。こういったことが重なると、やはり精神的な負荷が重なって疲れてしまいます。 また、話の展開についても、国による違いがあります。私たち日本人はアメリカ的な教育を受けているので、論理的な話し方をしますが、そうではない場合も多く、話を聞いていても「結論」がなくて、結局何が言いたかったのかよくわからないことが少なくありません。そうすると、通訳して伝える際に意図がわからず適切な言葉が選べなくなるので大変です。ビジネスのグローバル化の進展に伴って、今後もいろいろな国の人の通訳をする機会が増えていくことを鑑みると、私たち通訳も「正統派の英語を聞き取れるからリスニングは大丈夫」、というわけにはいかない時代がやってきていますね。最近は通訳者に限らず、ビジネスの現場でも非ネイティブの英語を聞く機会が増えています。リスニングトレーニングする時は、ネイティブの素材だけではなく非ネイティブがスピーカーの素材も取り入れて、慣れておくとよいでしょう。
Tさん:本当にそうですね。しかも、特にビジネスの世界では次々に新しいトレンド用語が生まれますし、業界ならではの専門用語も出てきますので、プロの通訳となった今もリスニングのトレーニングは欠かせません。
Nさん:確かに、リスニングを含めて英語の学びにゴールはありませんね。進化し続ける英語や、ますます多様化するビジネス環境に対応すべく、私たちプロの通訳にも常に学び続ける姿勢が求められていますね。
リスニング力UPにおすすめの方法・教材は?

―リスニング力を上げるには、どのようなトレーニングが効果的でしょうか?
Nさん:いろいろな意見があると思いますが、個人的には、「ネイティブの子どもが英語を学ぶ過程をたどる」のが良いのではないかと思っています。最近は、CrashCourseやKhan AcademyなどYouTubeでも、英語話者の子どもたち向けの動画がたくさん公開されていますから、それをひたすら聞いてみるのも良いと思います。また、他にも童話や昔話の動画などもおすすめです。英語の意味がわからなくても日本語で読んだり聞いたりしたことがある内容なので、知らない単語が出てきてもなんとなく意味を類推できるので飽きずに見続けることができますし、頭に英語が入ってきやすいからです。「浦島太郎」や「かちかち山」のような日本の昔話を英訳した動画を見つけて、シャドーイングをしながら視聴すると良いと思います 。大切なのは、自分の英語力のレベルに適したものを聞くこと。初心者がいきなり難しい内容を聞いても、全く理解できなくて、長続きしません。リスニングのトレーニングをするなら、少なくとも90%くらい理解できる題材から始めましょう。
―他には映画やドラマをトレーニングとして使うことを思い浮かべる人も多いと思いますがどうですか?
Tさん:映画やドラマに関しては、楽しんで聞ける点で初心者の入り口としては良いと思います。ただし、あらかじめ脚本として形になっている内容になるので、起承転結が定まっており、自然な発話になっていない点には注意が必要だと思います。また、役者の口の動きに合わせたワードチョイスになっているものが多いこともあり通訳トレーニングの素材としては不足しているように感じています。現場では自然な発話をその場で変換する必要があり、内容に起承転結があるものではなく、この先に何が話されるかのストーリー性を予測しながら通訳することが求められます。もしも通訳を目指すのであれば脚本仕立てではない素材をおすすめします。例えば、楽しんで聞きたいならポッドキャストのバラエティー生放送素材、より現場に近いものであれば、YouTubeでビジネスに関する講演などの素材、と自分の目的に合わせて選ぶのが良いでしょう。
―途中で知らない単語が出てきたら、その都度、調べたほうが良いのでしょうか?
Nさん:全体のメッセージを捉えられるものから始めて、わからないものを推測することが大切です。皆さん、限られた時間の中でトレーニングをされていると思うので、毎回すべての単語を調べていたら、時間が足りなくなってしまいますよね。ですから、わからない単語が出てきたら、その場で調べなくても、とりあえずメモをとっておくだけでOK。本当に覚えておくべき重要な単語なら、必ず、その後もどこかで見聞きするので、その経験が積み重なると意味を類推できるようになります。
Tさん:本当に覚えておくべき重要な単語なら、必ず、その後もどこかで「あの時に聞いたかも?」って戻ってきますよね。
Nさん:リスニングのトレーニングを毎日続けることの大切さも、そこにあります。先ほど、リスニング→発話→短期記憶の努力モデルの話をしましたが、1回聞いてわからない・覚えられない言葉も、2回、3回と聞いているうちにだんだん長期記憶として定着するんですよね。例えば浦島太郎でいうと、最初にturtleっていう単語を知らなくても、推測がつくような内容で先ず出会い、その後2度3度と聞いていると、turtle=亀だということがわかってくる。そうして理解した単語は、辞書で調べた単語よりも記憶に残りやすいものです。

―その他、リスニング力を上げるために意識していることはありますか?
Tさん:難しいことや興味がないことにも、アレルギー反応を起こさないことですね。例えば地下アイドルとか人工衛星とか、まったく自分に関心がない話題でも、ニュース番組やウェブサイトなどで取り上げられていたら、とりあえず読んだり聞いたりしておくことが大切です。そういった媒体で取り上げられているということは、程度の差はあれど、話題性があるテーマということですから、通訳の現場で話題になる可能性は大いにあります。
Nさん:本当にそうですね。以前、あるベテラン通訳の方が「通訳は真っ暗なトンネルの中に入って行く行為」とおっしゃいましたが、まさにその通り。どんなに資料で事前準備をしていても、話し手の思い付きや気まぐれで、真っ暗な中から球が飛んでくることは(予想外の話題が飛び出すなど)日常茶飯事です。そんなときにも慌てず柔軟に対応できるように、できる限りいろいろなことに興味を持って情報収集するようにしたいものです。
Tさん:そういったことも含めて、リスニング能力を高めるのに必要なことって、突き詰めると「ボリューム」だと思うんですよ。いかにして多くの英語を聞くか、いかにして多くの情報に触れておくか。そして何より、いかに多くの会話を経験するのかに尽きると思います。また、常にアクセントや語彙が綺麗なもので聞けるわけでもないので、綺麗なわかりやすいものから始めつつ、そうではないものを聞くことも大切です。
Nさん:さらに言えば、継続も大切ですね。1週間に1度まとめて聞くのではなく、少しずつでもいいので毎日継続して聞く習慣をつけてみる。先程、Tさんが言っていたようにニュースを聞いたり読んだりする習慣をつけることが本当に大切です。かくいう私も、通訳になってもう20年以上経ちますが、まだまだ勉強は継続中で、毎日できるだけ多くの情報に触れるように努めています。
Tさん:謙虚な気持ちは大切ですよね。自分が未熟であるという自覚がなくなると、成長も止まってしまいます。少しずつでも成長していく喜びを感じながら、何より自分の知らない世界を知ることを楽しみながら学び続けたいですね。私もまだまだ勉強中。初心を忘れず、皆さんと一緒に学び続けていきたいと思います。
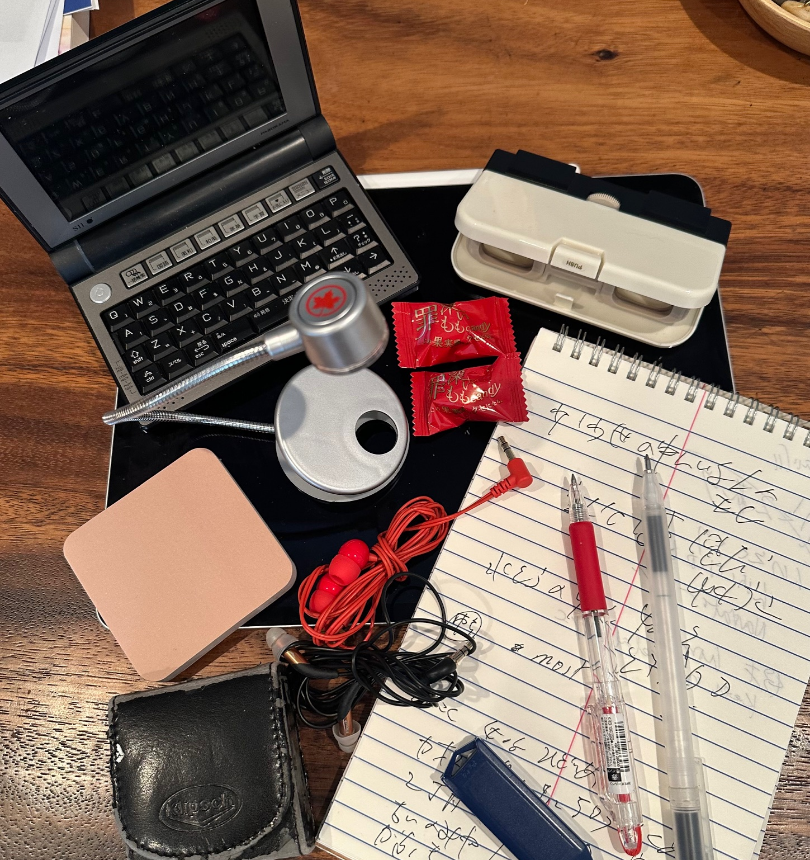
↑Nさんが常に持ち歩いている勉強&通訳グッズ
まとめ
リスニングは通訳の基本。ダニエル・ジルの有名な「努力モデル」でも、努力の筆頭にリスニングが挙げられている。
最近は英語でビジネスをする非ネイティブが増えているため、商談や国際会議の場で癖や訛りのある英語を訳さなければならない場面が増えている。正統派の英語だけでなく、非ネイティブが話す正統派ではない英語を聞き取るリスニング力が求められるようになっている。
リスニングのトレーニングは、90%くらい内容を理解している題材を使い、全体のメッセージを捉えながら、わからない単語を推測することが大切。毎日少しずつでも継続して取り組むことが大切。
おすすめの教材は、初級者にはネイティブの子どもが視聴する簡単な童話や昔話の動画、中級者には小中学生向け時事・社会教育動画。内容を知っている話なら、英単語など詳細部分がわからなくても、楽しみながら聞くことができる。聞きながらシャドーイングをするとより効果的である。上級者はひたすら日々のニュースを聴くことがおすすめ。
どんな話題でも聞き取って訳せるように、日ごろからいろいろな分野に興味を持って、見たり聞いたりして情報の「引き出し」を増やしておこう。
リスニングスキル向上に、ゴールはなし。コツコツと楽しみながら学び続けることが大切である。
▽対談者プロフィール
Nさん
日本で一般企業勤務後、渡米。ニューヨーク州立大学文学部博士号を取得。
米国のソニー系半導体企業(当時)で社内通訳者を経たのち、フリーランス通訳者として活動。
帰国後2015年に自身で通訳会社の(株)STCを立ち上げる。
現在も会議通訳、訴訟通訳の領域で現役通訳者として活動しながら、2023年4月より、東京女子大学国際英語学科特任准教授を務め、若手の育成にも力を注いでいる。
Tさん
米国生まれ。英語教育/言語学を専門とし、大学卒業(修士)後、TESOL資格取得。
拠点を日本に移し、外務省で通訳講師・私立大学で言語学講師を務め、語学検定の監修なども手掛ける。
同時にフリーランスおよびインハウス通訳者としても活動、国際関係・法律・宇宙研究開発・IT・機械など
幅広い領域の通訳に対応し活躍中。
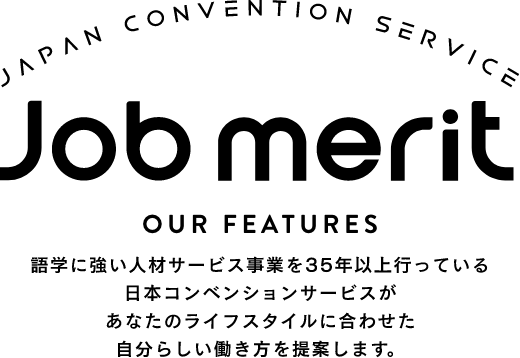
ジョブメリでお仕事を探そう
語学・イベント案件に強い!
正社員・派遣社員からアルバイトまで働き方いろいろ!
あなたのキャリアプラン・ライフスタイルにあったおしごとをジョブメリで探そう
このカテゴリーのおすすめ記事